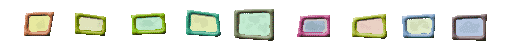
雨飾山
(あまかざりやま)
1963m
クリック


登山ルート 雨飾山 日本画
ギャラリ-Chappyに戻る
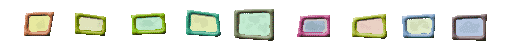
雨飾山
(あまかざりやま)
1963m
クリック

登山ルート 雨飾山 日本画
| 深田久弥「日本百名山」から 雨飾山という山を知ったのは、いつの頃だったかしら。信州の大町から糸魚川を辿って,佐野坂を越えたあたりで、遙か北のかたに、特別高くはないが品のいい形をしたピラミッドが見えた。しかしそれは、街道のすぐ左手に立ち並んだ後立山連峰の威圧的な壮観に眼を奪われる旅行者にはほとんど気付かれぬ、つつましやかな、むしろ可愛らしいと言いたいような山であった。私はその山に心を引かれた。雨飾山という名前も気に入った。北面の梶山新湯から、その雨飾山に登ろうとしたのは、太平洋戦争の始まる前であった。その頃はまだハッキリした登山路がなく、さんざん道を探しあぐねた末、とうとう分からず仕舞いで引き返した。しかし北側から仰いだ雨飾山はよかった。左右に均整の取れた肩を長く張って、その上に、猫の耳のように二つのピークが睦まじげに寄り添って、すっきりと五月の空に立っていた。やはり品がよく美しかった。それからしばらくして、今度は南側から登るつもりで、小谷(おたり)温泉へ行った。こちらからも道はなく、私は山に詳しい土地の人を案内に頼んでもらった。しかし来る日も来る日も雨で、四日間も待ったが、ついに空しく引き上げねばならなかった。三度目の雨飾山は、戦後のある年の十月下旬であった。そして私の長い間の憧れが今度は達せられた。登山口はやはり小谷温泉を選んだが、道は途中までしかなかった。頼んだ案内人を先に立てて、私たち四人はみごとな紅葉で塗りつぶされた山へ向かった。大海川(おおみがわ)へ入るともう道は消え、河原伝いに遡って行くほかなかった。大海川は上流で二つに分かれ、私たちは左の荒菅沢(アラスゲサワ)を採った。それまで比較的ゆるやかだった谷が、にわかに急な沢となり、石を飛び越えたり、へつったり、滝を避けるために藪の中を高捲きしたりせねばならなかった。沢筋に水が無くなって、ゴロゴロした大きな石を踏んで行くようになると、もう森林帯を抜け出て、見晴らしが展け、すぐ頭上にすばらしい岩壁が現れた。それはフトンビシと呼ばれる巨大な岩で、その岩の間に廊下のような細い隙間が通じていた。その咽喉を通り抜けて上に出ると、すでに沢の源頭で、あとは枯れた草つきの急斜面を登るだけであった。急登にあえぎながら稜線に辿りつくと、ハッキリした道がついていた。それは近年梶山新湯から開かれた登山道であった。それから頂上まで、急ではあったが、一登りにすぎなかった。ついに私は久恋の頂きに立った。しかも天は隈なく晴れて、秋の午後三時の太陽は、見渡す山々の上に静かな光をおいていた。すべての頂には憩いがある。梢にはそよとの風もなく、小鳥は森に黙した。風化し摩滅した石の祠と数体の小さな石仏の傍らに、私たちは身を横たえて、ただ静寂な時の過ぎるのに任せた。古い石仏は越後の方へ向いていた。その行手には、日本海を越えて、能登半島の長い腕が見えた。一休みして、私たちはもう一つのピークの上へ行った。案外近く、三十メートルほどしか離れていなかった。下から眺めてあんなに美しかった、その二つの耳の上に立った喜びで、私の幸福には限りがなかった。 次のページへ |